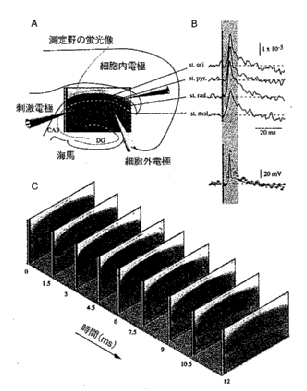4. 計測結果
ブレインビジョン株式会社 市川道教
前項で紹介したカメラシステムと光学系を用いて、脳を生きたままスライスして得た試料をDi-4-ANEPPS色素で染色して、小さな電気刺激を与えたときの観測結果を図5に示す。図5Aに示したのは、摘出したラット脳に対する観測部位と電極などの配置を示した図である。観測領域は海馬の中でもCA1と呼ばれる部分である。刺激電極をCA1領域のおもな入力線維であるシェーファー側枝に配置し、短いパルスで電気刺激する。刺激はシェーファー側枝を通じて、CA1の錐体細胞を次々に興奮させていく。その様子が、図5Cからよくわかる。この映像は、もともと0.75msec単位で測定されているが、図の都合で1枚おき、すなわち1.5msecごとの映像を示した。本来、膜電位感受性色素の神経興奮による変化は0.3%程度なので、コンピュータ処理により変化成分だけを約300倍に強調し、赤い色をつけて映像にスーパーインポーズして示した。赤の濃い部分がより脱分極している部位である。このように、実時間で膜電位を2次元でイメージングできるのが、この方法の最大のメリットである。さらに、図5Bに示したのは、スライスの任意の点(この場合CA1の錐体細胞の各場所に当たる4ヵ所)を選び、その点での神経活動を時間方向に解析した表示である。これはちょうど、複数の内部電極を刺したときとほぼ等価であるが、実際には、同時に映像として記録した各画素のデータを読み取ったものである。つまり、この画像上の任意の点に内部電極が存在していると思えばよい。図5Bで、4つのトレースの下に示したノイズの少ない実線は、内部電極で記録した活動電位であり、赤い小さな丸で示したのは、ほぼ同じ場所の光計測の結果である。このように、ほとんど同じ波形が得られることがわかる。しかし、よく見ると、活動電位のピークに比較して、遅い成分が光計測ではやや大きめに写る。これには、①光で観察される活動電位はいくつかの細胞の平均値なので、速い活動電位は同期性が悪く、実際よりも小さめに観察される、②膜電位感受性色素の測定量は膜電位と同様に膜の密度にも比例する。この試料では、神経細胞膜の密度がデンドライトで高く、細胞体で低いため、デンドライトの成分が混じるとシナプス電位成分が強調される、という2つの理由が考えられる。膜電位感受性色素を用いた研究では、組織による染色性の違いやアクティブな膜の密度について考慮する必要がある。なお、一部色素(たとえば、RH-155)は、神経細胞よりもグリアによく取り込まれるため、グリアの比較的遅い分極がデータに混入することが知られている。この測定に用いたDi-4-ANEPPSは、神経細胞の活動に依存する蛍光変化がほぼ全てであり、グリア活動はほとんど見えない。まったく新しい試料の場合には、使用する色素との相性などを調べてから詳しい実験に進むべきである。
おわりに
膜電位感受性色素による神経興奮活動の計測は、いくつかのポイントをつかめば、難しい方法ではない。また、この技術は歴史的には古く、すでに開発されて20年が経過している。しかしながら、いまだに一般に難しい技術と考えられている。その理由は、計測に適したカメラシステムが入手困難なことと、システマティックに安定な計測を実現する地道なデータの積み重ねが後になり、派手な結果を求めてきたためではないかと反省する。われわれの研究の1つの方向性は、誰でも可能な光計測技術を完成することである。それと同期して、世界中の研究機関で、GFP(クラゲ由来の緑色蛍光タンパク質)をチャネルタンパク質に遺伝子レベルで導入する研究も進展している。近い将来、生まれながらに電飾することなく膜電位で蛍光変化する脳をもつ実験動物が誕生する可能性がある。そうなれば、一気に普及することになるだろう。
さて、今のところ、ヒトを対象とした医療診断に実施例はない。その最大の理由は、MRIのようにまったく無侵襲な手法と異なり、診断する部位が見える状態でないとならないからである。また、色素の毒性も少ないとはいえ、安全とは言い切れない。しかしながら、米国の医科系大学を中心に心臓手術や脳外科手術の現場で確度を高めるための補助的な手段としての応用を検討していると聞く。何年か先には、多くの生命を救える手法に発展するかもしれない。その日の到来をねがって、本節の結びとしたい。
(出典 共立出版 「光による医学診断」(2001年3月30日出版))